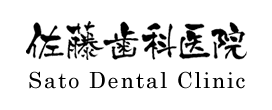スタッフブログ
学会
ブログを長い間、サボってしました。
色々な情報を皆さんにお届けしようとこれからも少しずつではありますが、お口に関しての情報発信をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。
先日、所属しております日本歯周病学会に出席してきました。
最新の歯周病研究の発表や、それを基に臨床への応用をおこなったりと、本当にいつも勉強になる場所であります。
20年以上も歯周病を治療してきた著名な先生のお話には、長く診てきた経験とノウハウがいっぱい詰まっておりました。
これからも定期的に学会に出席し、日々の診察に活かしていきたいと思います。
春

春到来~!
東京近郊では桜が散って葉桜に変わってきています。
春は、今年度の始まりということで清々しい感じが致します。
せっかくですから、お口の中も掃除し、スッキリ清々しくしませんか?
当医院では定期的に掃除をすることで、予防的お口のメンテナンスを行うことを勧めております。
予防的にお口のメンテナンスを行うことで、虫歯・歯周病が早期に悪化することを防ぎます。
特に症状がなくても今後の起こり得る症状などもご説明致しますので、歯医者久々の方々もお待ちしております。
歯周病の治療�A
さて、歯周基本治療が終わったのですが、まだ歯周ポケットが深く出血や排膿(膿が出てくること)が診られる場合どうしたらいいのでしょう
環境がよい状態まできた場合、歯を抜かず頑張って治療する方法としては 『歯周外科手術』 という治療法があります。
この手術の目的は
1.歯周ポケットの除去、もしくは改善
2.歯周組織の形態を修正することで、ブラッシングなどの口腔清掃をしやすくすること
3.スケーリング、ルートプレーニング時に根面への器具を到達しやすくすること
4.破壊された歯周組織の再生を図り、歯を抜かないよう保存させること
上記のそれぞれの目的のために色々な手術方法はあります。
歯周基本治療だけでは足りなかった治療を手術をして補う、といった感じです。
「手術」ということですので、当然歯肉を切って、歯を骨に埋まっている部分まで見えるようにしていきます。
そこから、それぞれの目的に合う手術法に従って、手術を行っていきます。
ここで一番大切なことは
その手術をして歯を抜かない済んでも、今後も今まで以上に口腔内をキレイに保っていないと
また歯が抜けてしまうほどになってしまう、という事です。
やっぱり基本は 『歯ブラシの仕方』 です。
しっかりとした歯ブラシの仕方を行い、歯周基本治療が終わるまで
頑張って口腔環境を整えていきましょう。

歯周病の治療法�@
歯周病の治療はどのように行われているのでしょうか?
歯周病の進行程度によるのですが、治療でもっとも大切な事は
『患者さんのお口の中への意識』と『患者さん自身の努力』とも言えます。
歯科医院での治療は基本的に歯科衛生士によるプラーク〈歯垢〉と歯石除去になります。
歯石は歯に付着したプラーク〈歯垢〉が唾液と反応して石灰化してもので、容易に除去できない歯の沈着物です。
歯石にも種類があり、歯の表面に付着している黄色~茶色の歯石は縁上歯石と言い、
歯肉の中、歯周ポケットの中に入りこんでいる褐色~黒色の歯石を縁下歯石と言います。
縁上歯石は歯面への固着力は弱いため、スケーラーという器具で取り除く事ができます。
下図のように、少し歯周病がすすんでポケット内に付着した歯石が縁下歯石なります。
歯面への固着力は強いため、除去が大変困難になります。

この状態では歯肉も腫れていますので、歯ブラシだけでも出血致します。


キュレットという器具を使い、強固に付着した縁下歯石を取っていきます(歯から歯石を削ぎ取る感じです)

ここまで歯周病が進行してしまうと、歯が揺れてしまうため強固に付着した歯石を取り除くのが大変になります。
さらに歯周ポケットが深く器具がポケット底まで届かないため、縁下歯石の取り残しが起きてきます。
そのため、このような重症化したケースには、外科的に病巣や歯石を取り除く歯周外科という次なる治療法へ移行していきます。
上図のように歯石を放っておいたまま歯周病が進んでしまうと、治療をすることも複雑で大変になってきますので
定期的に歯科医院で歯石を取ように心掛けましょう。
あけましておめでとうございます。
歯周病の診断
歯周病の診断は歯周ポケットの深さにより、治療方針が決まります。
歯周病は
①問診
②歯周ポケット検査
③歯周組織状態の確認 /口腔内写真
④x線検査
以上、4項目で診断し治療方針を決定していきます。

歯周病に関しての問診が終わりましたら、歯周ポケット検査を行っていきます。
目盛のついた細い棒状の器具(プローブ)を歯と歯肉の境目に入れて、歯周ポケットの深さを測ります。
この深さ(プロービングデプス)によって歯周病の程度を決めていきます。
2mm以下:健康な歯肉
2~6mm:軽度~中程度の歯周病
6mm以上:重度の歯周病
この他にも、歯周ポケット内からの出血/排膿の有無や歯の動きが正常な範囲かどうか、を検査していきます。
歯周ポケット検査とx線検査の画像から、どの程度歯周病が進行しているか判断し、治療を進めていくことになります。
基本的には、虫歯の治療を行うまえに歯周病の治療を行うのが一般的な歯科治療です。
当医院では歯周基本治療を行いながら、必要であれば虫歯の治療を並行して行うようにしております。
年末年始の診療時間
忘年会
先日、少し早いですが佐藤歯科医院の忘年会を行いました。
この時期どうしても暴飲暴食気味で、体が疲れやすいと思います。
実際、私も忙しくて?!飲みすぎで?! 疲れてますTT
お酒を飲むと口が渇きます。口が渇くと虫歯・歯周病菌の絶好のチャンスとばかりに動き出します。
酔って家に帰っても、キチンと歯を磨きましょう。
歯も磨いて、口腔の環境も整えておけば、風邪も引きにくいです。
寒さも厳しくなってきていますので、お体には十分お気をつけて下さい。
歯周組織を壊す歯周病�A
歯周ポケットが出来る過程は前回ご説明しました。
そのままその歯周ポケットを放置していたらどうなるのか?
歯周ポケット内の細菌が繁殖し、歯周組織の中の一つ、歯を支えている歯槽骨が溶かされて、ついには歯が抜けてしまうことになります。
さらに歯周病は中年以降 『喫煙』 『肥満などの生活習慣病(メタボ)』 『糖尿病など免疫力低下』 などでも悪化する可能性があります。

なかでも 喫煙は、有害物質(ニコチン)が末梢血管の循環を阻害し、(歯肉の端までの血流を妨害してします)
それにより局所的な免疫機能は低下、組織修復機能の低下を起こし、さらなる歯周病の悪化へとつながります。
無症状で進行するため、歯肉からの出血に気が付いても 『仕事忙しいし、いいや、、、。』 と言って、見過ごしてしまう方も多いと思います。
そのまま初期段階を過ぎ、歯周病中期になると唾液はネバネバして、口臭が強く、歯が少しぐらつき始めます。
重症化すると、上記に示した唾液・口臭はもちろんの事、歯が痛くて物も噛めなくなります。
見た目や症状では気が付かない『歯周病』
年齢とともに全身に関わってきますので、今のうちからきちんとした口腔ケアの仕方を覚えておきましょう。
歯周組織を壊す歯周病�@
歯は 歯肉、 セメント質、 歯根膜 、歯槽骨から構成される 『歯周組織』 によって支えられており、容易には抜けないようなっています。
歯周病は、その歯周組織は侵される感染症です。

健康な状態でも、歯と歯肉の境目には、小さな溝(歯肉溝)があり、汚れがたまりやすくなっている。
キチンとした歯みがきで汚れを取り除いていれば問題ないのですが、口腔ケアを怠ると、この溝にネバネバした物質がたまってきます。これが 細菌の塊、 プラークです。
プラーク を放置しておくと、プラーク内の細菌 によって歯肉に炎症が起こり腫れてきます。
その腫れによって、歯と歯肉の溝が広がって 『歯周ポケット』 が形成されてきます。
プラーク は、当初は柔らかいので、歯みがきや歯間ブラシ、フロスといったもので取り除くことは出来ますが、時間が経つと硬くなり除去しにくい 歯石 となります。
歯石 は専門的な器具を用いないと、取り除くことは難しくなります。
『歯周ポケット』 の中に、プラーク や 歯石 が付着してくると、ますます 歯周ポケット が深くなっていきますが、この段階で歯科医院を受診し、プラークや歯石を取り除く治療を受け、
さらに歯ブラシが適切に出来ているか指導を受けてそのように歯ブラシの仕方を改善していけば歯周ポケットは減少してきます。(プラークが減り、歯肉の腫れが引いてくれば歯周ポケットは減少する)
歯周ポケットが形成されている場合、歯石は1~2回スケーリング〈歯石除去)では取り除く事が出来ない場合があります。
たまに患者さんの中には『1回で全部やって欲しい』とおっしゃる方もおられますが、歯石除去を行って、歯肉の腫れが改善出来たところまで確認して、初めて歯周病の治療が終わる、という過程を理解して頂きたいと思います。
歯周病は重度にならないと症状がほとんどないため、きちんとした口腔ケアが必要と当医院では考えております。


初診相談・カウンセリング
治療に関する疑問や不安にお答えします。無理に治療を進めることはありません。是非一度ご相談下さい。
- 名称
- 佐藤歯科医院
- 院長
- 佐藤 正賢
- 住所
- 東京都品川区東五反田1丁目12-12 落合ビル1F
- 電話番号
- 03-5475-6480
- メール
- お問い合わせフォームはこちら
- URL
- https://www.sato-sika.com/
- アクセス
- 都営浅草線五反田駅A6出口すぐ前
JR山手線五反田駅東口より徒歩3分
日比谷線の高輪台駅A1出口より徒歩7分
- Address
- 東京都品川区東五反田1丁目12-12
落合ビル1F